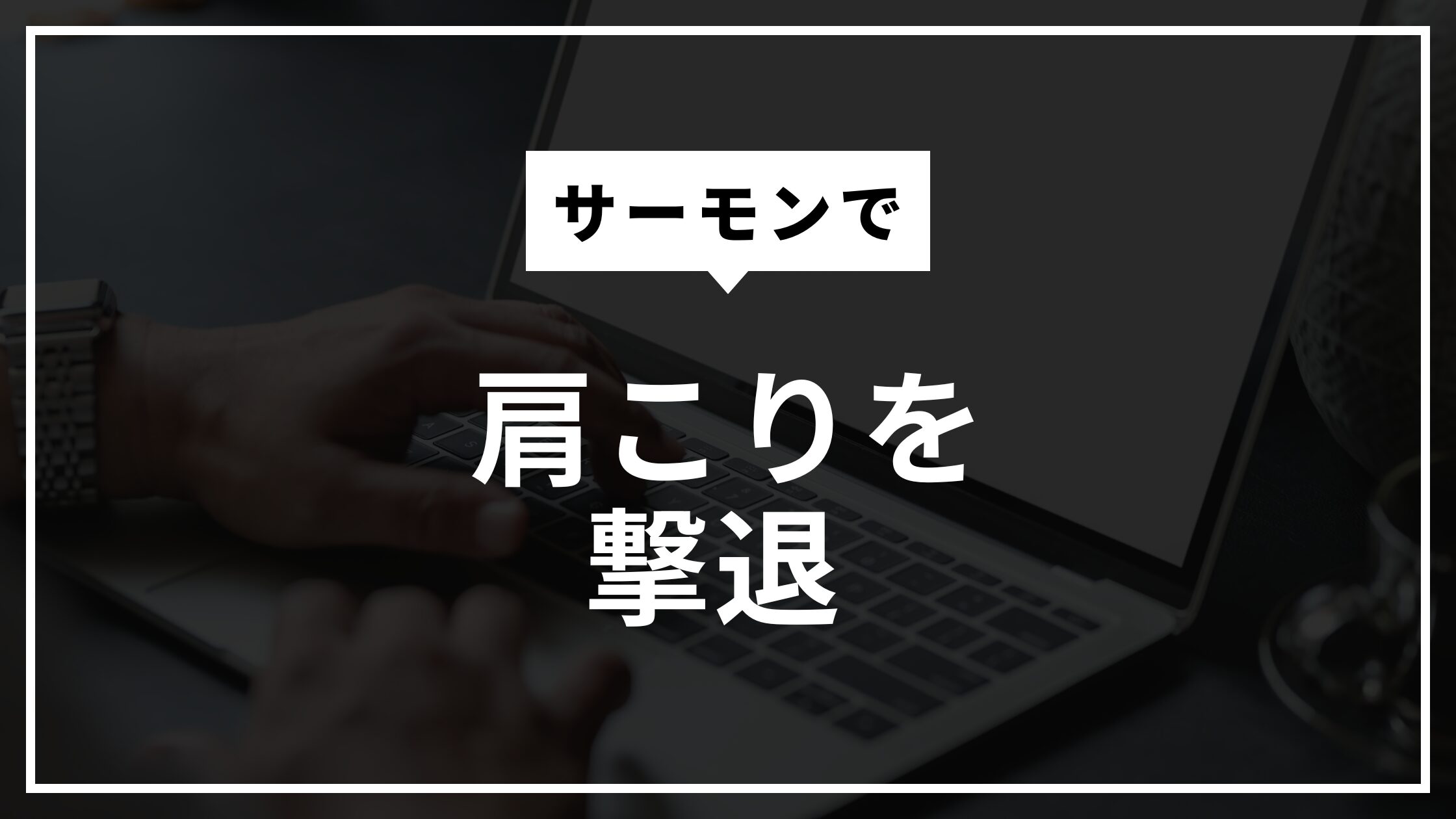肩こりとは?原因とメカニズム
肩こりとは、肩周囲の筋肉が持続的に緊張し、硬くなって血流が滞ることで、痛みや不快感を引き起こす状態を指します。しかし、単なる「筋肉の疲労」と片付けてしまうのは不十分です。肩こりは、筋肉、神経、血管、関節、さらには自律神経のバランスが崩れた結果として発生します。では、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
1. 筋肉の緊張と血流の低下
肩こりを引き起こす主な筋肉は、「僧帽筋」「肩甲挙筋」「菱形筋」「胸鎖乳突筋」などです。特に僧帽筋は、首から肩、背中にかけて広範囲に広がる大きな筋肉で、デスクワークやスマートフォンの使用で持続的に緊張しやすい部位です。
筋肉が緊張すると、筋繊維が縮まり、周囲の毛細血管が圧迫されます。その結果、筋肉に必要な酸素や栄養が不足し、老廃物の排出も滞ります。これが「筋肉の硬直」と「痛み」の原因になります。
2. 神経の過敏化
筋肉の硬直が続くと、筋肉の内部に存在する「筋紡錘(きんぼうすい)」という感覚受容器が異常に興奮し、脳へ過剰な「痛みの信号」を送ります。これにより、実際のダメージ以上に「肩がこる」「痛い」と感じることになります。これは「神経の過敏化」と呼ばれ、慢性的な肩こりの一因となります。
さらに、肩の周囲には「交感神経」と「副交感神経」という自律神経が走っています。筋肉の緊張によって交感神経が優位になると、血管が収縮し、ますます血流が悪くなる悪循環に陥ります。
3. 呼吸の浅さが肩こりを悪化させる
意外に思われるかもしれませんが、「呼吸の浅さ」も肩こりの原因の一つです。ストレスや姿勢の悪化により、胸式呼吸(浅い呼吸)が続くと、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が過度に緊張します。この状態では、肩甲骨の動きが制限され、僧帽筋や肩甲挙筋に負担がかかります。
また、横隔膜の動きが悪くなると、副交感神経の働きが低下し、肩こりを慢性化させる原因となります。つまり、深い腹式呼吸を意識することが、肩こり改善の鍵を握るのです。
4. 姿勢の崩れが肩こりを助長する
悪い姿勢は肩こりの大きな要因です。特に、デスクワークでありがちな「頭部前方位(頭が前に出る姿勢)」は、首や肩に大きな負担をかけます。頭の重さは約5kgありますが、首が前に傾くと、その負担は2倍、3倍にもなります。
また、「巻き肩(肩が内側に入る)」の姿勢も肩こりを引き起こします。胸の筋肉が縮み、背中の筋肉が引っ張られることで、肩甲骨の動きが制限されるからです。

5. 肩こりの「根本原因」を考える
ここまで見てきたように、肩こりは単なる「筋肉の疲労」ではなく、筋肉の緊張、血流障害、神経の過敏化、呼吸の浅さ、姿勢の崩れ など、複数の要因が絡み合っています。
肩こりを本質的に改善するには、「筋肉をほぐす」だけでなく、血流を促進する、神経の働きを正常化する、呼吸を整える、姿勢を改善する といった総合的なアプローチが必要です。
次回は、「肩こりの種類」について詳しく解説し、それぞれの対策をお伝えします。